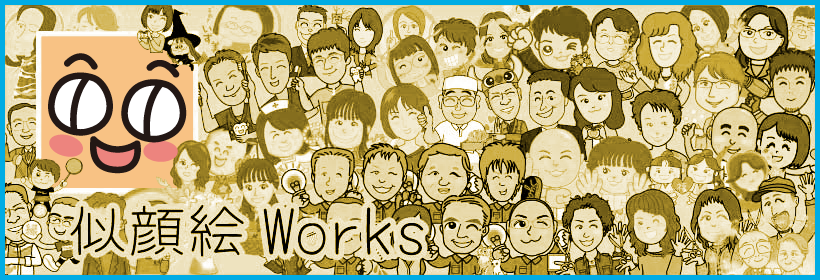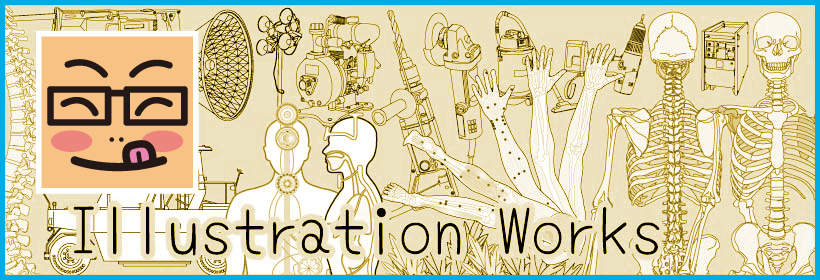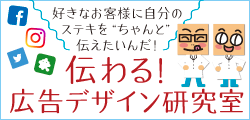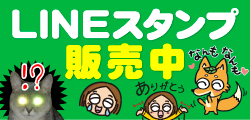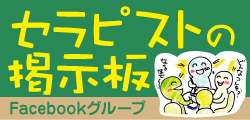- ホーム
- 伝わる!広告デザイン研究室
- 広告デザイン研究室
- デザイナーになるにはどうしたら良いの?
デザイナーになるにはどうしたら良いの?
2020/02/17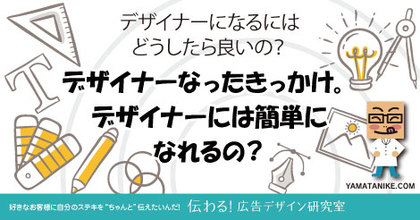
デザイナーなったきっかけ。

デザイナーになるのに簡単な時代だったかも。。。。
高校を卒業して、美術大学に入るか専門学校に行くかで道は分かれると思いますが、私たち「やまたに家」は夫婦でデザイナーです。デザイン会社に就職してすぐにデザイナーに?
デザイン会社に入ってからの修行が始まるんです。
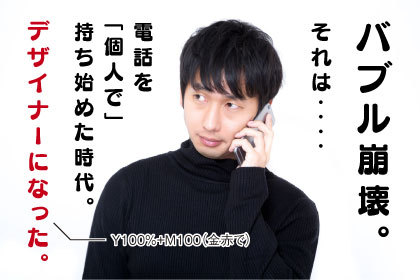

今みたいに、パソコンで作ってネット印刷で「ポンッ」と終了ではなかったんですよ。

・クライアントと打ち合わせ(営業・ディレクターが打ち合わせ)
・デザインカンプ作成(ディレクター・チーフデザイナーが作成)
・デザイン提出(デザイナーがデザインして、営業がクライアントに提出)
・デザイン修正(デザイナーが修正して、チーフがチェック)
・デザインOK(クライアント様のデザインチェックで校了をいただく)
・入稿データ作成(デザイナーが色指定や、各印刷に必要な写真や資料を揃える)
・印刷会社・工場へデータ入稿(デザイン会社から来た、版下や必要なものを加工して印刷)
・印刷物やグッズが完成、クライアントへの配送(印刷チェック・商品チェックを済ませ、お客さまの手元に)
パソコンが普及して楽になったのか?

DTPとはdesktop publishingの略です。
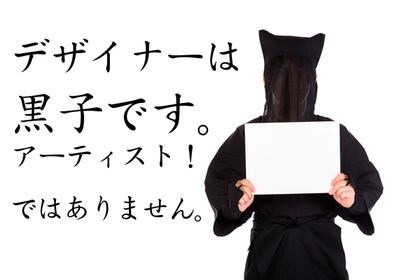
「デジタル大辞泉」の解説では、「パソコンなどを用いて、原稿の入力から編集・レイアウト・印刷などの出版のための作業を行うこと。」と表記されいますが、「パソコンで作って印刷する」って意味だと!今現在デザイナーになりたい人にとっては近道なのかもしれません。あまり、人と関わらずとも己自身でパソン一台あれば、デザイン・印刷・納品の工程をご自身でやれちゃうのも今の時代だと思ってます。簡単にデザイナーて名乗れちゃいますもんね。
ただし自分でデザイナーと名乗っていても、クライアント様の想いを形にするのが「デザイナー」です。決してアーティストではなく。黒子に徹してこそデザイナーだと私は思っておりますが、クライアント様に寄り添い考え、アイディアを共に出し合って補うのもデザイナーだと思えるんです。
デザイナーになりたいのなら、クライアントの意図を汲み取り形にして行くのが近道です。
-
 似顔絵もここまで使われると本望です!
暑い日が続いている札幌。とはいえ本州の方に比べたらまだまだ涼しいので弱音は控えたい…スタジオシンカーやまたに家
似顔絵もここまで使われると本望です!
暑い日が続いている札幌。とはいえ本州の方に比べたらまだまだ涼しいので弱音は控えたい…スタジオシンカーやまたに家
-
 ホームページは●●を発揮したらいい!
昨日7月11日(月)はオンライン(zoom)にて、分身ホームページ『穂口になんでも聞けるで会』好物食べ
ホームページは●●を発揮したらいい!
昨日7月11日(月)はオンライン(zoom)にて、分身ホームページ『穂口になんでも聞けるで会』好物食べ
-
 好きなお客様に選ばれたい!〜ホームページって役立つの?
個人で活動、スモールビジネスを応援!! 広告デザインのスタジオシンカーやまた
好きなお客様に選ばれたい!〜ホームページって役立つの?
個人で活動、スモールビジネスを応援!! 広告デザインのスタジオシンカーやまた
-
 デザインは自由に!トキメキを大事に〜趣味もデザインに活かせる♪
先日、小樽のガラス作家 SHiMA SHiMAさんに誘われて、なわ あいさんの「アルコールインクアート」のワー
デザインは自由に!トキメキを大事に〜趣味もデザインに活かせる♪
先日、小樽のガラス作家 SHiMA SHiMAさんに誘われて、なわ あいさんの「アルコールインクアート」のワー
-
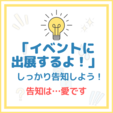 「イベントに出展するよ!」しっかり告知しよう♪告知は…愛です
イベント出展は知ってももらえるチャンス!出展のその前にしたいこと。 自分のお店を離れて、イベントや●●展に出展
「イベントに出展するよ!」しっかり告知しよう♪告知は…愛です
イベント出展は知ってももらえるチャンス!出展のその前にしたいこと。 自分のお店を離れて、イベントや●●展に出展

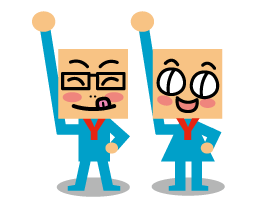
広告デザインのスタジオシンカー[やまたに家]
デザインはあなたが羽ばたく翼になる!
まずはお気軽にお問合せくださいね。
電話番号:011-785-2873
所在地 :北海道札幌市東区北23条東16丁目1-19 2F
営業時間:9:30〜18:00
定休日 :不定休